こんにちは。「社会福祉士相談所 LOVE」です。
昨日のことになってしまいましたが、当事業所代表が、NPO法人 ペアレントメンターかがわ 様主催の公開講座『保護者の本音と願いに寄り添うペアレントメンターによる支援』を聴講してきました。
講座の内容を長々と書いても冗長になってしまうだけなので、お話の中で当事業所代表自身が印象に残ったことと、当事業所代表なりに考えさせられたこと(当事業所代表なりの考え)に絞って、部分的に記します。なお、講座の中で講師やパネリストの方々がお話されたことは黒字、当事業所代表が考えたことは緑字で記します。
○発達に課題がある『子ども』については多くの支援策・制度があり、専門職も関心を示すが、「自分の子どもの発達が同年代の子どもと違う」と感じる保護者の葛藤やモヤモヤを支援する制度がない。
正直、全く考えたこともなかったけれど…。言われてみれば本当にそうですよね。当事業所代表自身も障がい者(当事者)なので、どうしても「当事者の特性に配慮した支援を!」と声高に訴えてしまうけれど、保護者や家族、周囲の方々にも、それぞれの立場でのしんどさ・悩みがあるはずですよね…。ハッとさせられました。
また、要介護(要支援)高齢者を支援する「介護保険制度」も、具体的な不自由さを支援するためのたくさんのメニューが用意されているけれど、要介護(要支援)高齢者や家族の心理面での葛藤を手当てする方策は、(制度としては)用意されていないですよね…。
○専門職の役割は、『見通しを示す』こと。そこが出来ていないから、当事者や家族が専門職の指導に乗りにくい。
耳が痛い。本当に耳が痛い。けれど、本当にそうですよね。ただ単に、「療育やリハビリテーションを頑張りましょう。就労支援施設に通って、就労に向けたトレーニングを頑張りましょう。」と伝えても、お相手にすれば、「いつまで頑張ればいいの?そのトレーニングをしたらどんな効果があるの?」ですよね。それをしっかりと答えられないと、「よく解らないけれど…。トレーニングしんどいよね…。ムリにやらなくても…。」というような発想になっても、不思議はないですよね。でも…。でも…。経験が浅い支援者にはとってもムズカシイことも事実…。
○「親の会」と「ペアレントメンター」は、目的が全く違う。
「親の会」は、「(親亡き後の)我が子のために」活動するので、「我が子(と同じような状況の方々)が、生きやすくなるために、法制度の制定を訴える。」というような行動が中心。
「ペアレントメンター」は、保護者の前向きな気持ちが途切れないように「支える」ことが役割。
○「当事者性」がある限り、悩みや葛藤が「無くなる」ことはあり得ない。けれど、支援がフィットすることでそれを「小さくする」ことは出来る。
はき違えてはいけない本当に大切な視点ですよね。
「社会福祉士(相談所)」としては、「当事業所が全て解決してあげる」と思ってはいけないし、間違っても言ってはいけない。(「問題解決の主体は当事者である」支援者にとって基本中の基本でしたよね。)
「一障がい当事者」としても、肝に銘じておくべきことですね。とは言え…。「当事者」は本当にしんどさが限界に達すると、それを忘れて(解らなくなって?)しまいがち。「経験者は語る」です。
それを、「自立支援」を信条とする専門職は、『依存』と呼び、忌み嫌うし、強く批判するのでしょうね…。だからこそ、「今の自分の立場(役割)は?」と冷静に考え行動する必要があるし、「専門職(有資格者)も生活を営む中で、何かの生活課題の当事者になり得る」ことを知っておく必要がある。「専門職者も生活者である。」という言説は、本来そういう意味で使うべきものだと思う。そんな時は、突き放す必要なんて全く無い。クライエントに対応するのと同じように、ゆっくり優しくエンパワーすることに全力を注げばいい。何か、「仕事とプライベートの分離」という側面がやたら強調される現状、嘆かわしく感じます。
○専門機関と繋がっても孤独
これは、完全に当事業所代表の考えですが、今の「契約(書)偏重主義」とも言える現状では、「そうでしょうね…。」と思います。
「契約(書)」も状況に応じて、「毎日(面接)」とか「週3回」とか、「3か月(半年)に1回」とか柔軟に対応出来るならまだしも、何かこういった相談支援面接の契約(書)は、判で押したように「月1回」と決められている場合が多い。その人のメンタル面の性質や、課題発生からの時期等によって、「月1回」が妥当かどうかなんて解らない。
余談ですが…。当事業所はそもそも「契約(書)」という概念を取り入れておりません。お相手の希望、双方の状況に応じて相談の上、「当面は、週3回は面接しましょうか。」、「随分落ち着いてこられましたね。月1回で大丈夫ではないかと思います。」、「必ずしも毎月面接する必要もないですよ。」と柔軟に決めれば良いと思いますし、「行きつ戻りつ」も当然あると思うので…。それをわざわざ「契約(書)」なんてものに残して、変更がある度に作り替えるなど、全く無意味。毎回の相談記録をきっちりと記録しておけば良いこと。それに、「契約(書)」というカタチにしてしまったら、その契約条件以上の相談支援を求めてくる方を、切り捨てざるを得なくなってしまう…。でも本当に支援を必要としているのは、むしろ決められた契約条件を守ることが出来ない程に混乱し、不安の只中に在る方々ではないのかと思います。
「頻回な相談希望をカスタマーハラスメントとして扱おうか。」なんて、昨今の風潮、溜め息と憤りしかありませんね。「全くもって、解っていない。」と感じます。
○「実は気になっていた。」のなら、早く伝えて!
講座の中では、支援者から「(当時)支援制度がないので、伝えたら絶望させるだけと思い、様子を見ていた。」と言われたということが言われ、それに対して、「障害の検査を」と伝えようと考えるなら、そうなるだろうが、「この子を見てて、こういう面が気になるから、一緒に考えていこう。」と伝えようとするなら、そうはならない(早く伝えられる)のではないかという意見が挙げられていました。
当事業所代表はそれに加えて、「そういう時に本当に伝えるべきメッセージは、”あなたたちご家族のことを気に掛けていますよ。”という気持ちではないのかと感じます。そのメッセージであれば、むしろ立ち居振る舞いを通して、支援者が常に発しておくべきメッセージだと思うのです。そして、孤独や不安に対する唯一の特効薬は、「気に掛けてくれる人の存在」に尽きると思います。
合わせて、当事業所代表自身の個人的な体験ですが、全く逆の、「気になっている気持ちを受け止めて!」ということもあると思います。当事業所代表自身も7,8年程前に「自身の発達障害」を疑い、検査等のアクションを起こす前に、当時信頼していた社会福祉士の先輩方に相談したことがありました。その時の答えは、「私はあなたが発達障害だとは思わない。」の一言で終わらされました。私の気持ちは、「安心した💖」というようなものでは全く無く、むしろ「貴方は医師か?」という怒りと、「私の不安な気持ちを全く受け止めて頂けなかった。」という失望だけでした。(結果、検査を受け、「グレーゾーン」判定を受けています。)
○「生きる力」よりも、『生きようとする力』
この講師の言葉を聴いて、「そうだよね。」と大きく頷くと同時に、「やはり大学教授様は凄い。」と思わされました(笑)。実は、当事業所代表が『依存』を否定的に考えていない理由もここにあります。
『依存』と言うと、とかくマイナスイメージで捉えられますが、当事業所代表は、「求めたら応じて頂けるということを知る、とても大切なこと。」と捉えています。「全面的に助けて。」と寄りかかった時、「いいよ。」と好きなだけ、もたれかけさせてもらえることで、人の暖かさを知れる。この社会は、棄てたものじゃないと思える。それがそのまま、『生きようとする力』になるのではないのでしょうか。そして、『生きようとする力』こそ、『自立心』と言い換えることが出来るものではないでしょうか。
それでなくとも、「発達の気になる方たち」は、「ダメ!」、「止めなさい!」、「違うでしょう!」、「何を甘えているの!」、「その考え方はおかしいよ。」、「そんな自分だけのワガママは通りませんよ!」という叱責の言葉をたくさんかけられてきたはず。そんな経験ばかりなら、「これからも頑張って生きて行こう。」、「頑張ってこの課題に取り組んでみよう。」、「SOSを出してみよう。」なんて、思えなかったとしても、何ら不思議はない。当事業所代表はそんな風に感じます。ただ、当事業所代表はこんな風(「生きる力」よりも『生きようとする力』ですよ!)に一言で表すことはできなかったけれど…。
当事業所代表にとって、とても感じることの多い講座であったため、思いのほか長くなってしまったかもしれません。最後までお読み頂き、ありがとうございました。

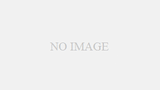
コメント