こんにちは。「社会福祉士相談所 LOVE」です。
2月に、「何処かと繋がれていれば…」というタイトルのブログ記事を執筆させて頂きましたが、インターネットを閲覧していると、こんな記事が目に留まりました。
母乳染ませたタオルで殺害「『母親なんだから』…その言葉は嫌いです」3人の子どもの遺体と暮らした女性の獄中手記
当事業所代表は、「この事件は、現在の日本社会にまん延する『自立』至上主義とも言える風潮が引き起こしたものではないか。」という考えを強く持っております。
現在の日本社会は、「『自立』して(人の助けを借りずに、出来ることなら福祉の支援サービスや社会保障制度のお世話にもならず、自分自身の力で困難を乗り越えていくこと)生きる」ことを求める思想が強過ぎる…。
そのため、「重度」(明らか)な障害を有している場合は、(やむを得ず)支援の対象と認識されるけれど、「軽度」(ボーダー)な障害の場合には、そもそも気付かれないことも多く、「努力が足りない!」と叱責の対象になってしまうことがあり得る。
とは言え実際には軽度の障害を有しているので、努力の成果が表れるまでにとても時間が掛かってしまうことも多い。「1日1歩」ではなくて、「数年掛かってようやく半歩」というようなこともザラにある…。結果、「何の努力もしていない」と誤解され、「見放されて」しまう…。
そんな時に、「よこしまな考えを隠して”優しく”接してくれる人」に出会ってしまったら…。喜んでついて行くよね…。誰からも見放されてとても寂しい思いでいる時に(そんな自分に)”優しく”声を掛けてもらえたら、嬉しいもの…。
記事のケースで言えば、彼女はこれまで、もの凄く努力し続けてきたのだと思う。だからこそ、「介護職」の仕事に就くことが出来たのだと思う。だけどそのことが、皮肉にも彼女の『障害』を周囲からより、見えづらくしてしまった…。
介護施設で働いていたのなら、生活相談員或いは生活支援員が配置されていたはず。社会福祉士資格を所持している職員も居たかもしれない。「もしかしたら彼女には、何らかのハンディキャップがあるのかもしれないな。」と気付かれてもおかしくなかったと思うし、当事業所代表に言わせれば気付かれなければならなかったと考えます。(当事業所代表が時に、福祉の支援者に対して「仕事していないよね!」というような痛烈な批判をすることがあるのも、こういった実態があるからです。)
ただ、現在の日本社会でそれはとても難しいことであるとも思います。何故なら、彼女が「職員(支援者)」として、同僚たちの目の前に現れたから…。
どこの『職場』でもそうだと思いますが、特に福祉の現場では、「職員」と「利用者」の間には、それこそ断絶されているかのごとく明確な線引きがされている。
「職員でありたいならば、自らの障害を消し去りなさい!」とでも言われんばかりの、無言・無意識の圧力を掛け続けられるといった感じでしょうか…。「非科学的な話」の極みですよね…。
かくいう当事業所代表も、このようなケースを見聞きした時、「何処かに相談されていれば…。」、「どうして相談しなかったのか…。」と、反射的に思ってしまいます。専門職として本当に恥ずべきことです。
でもそれについては、彼女自身が明確に反論して下さっていますし、発達障害を有しているのであれば、そもそも「相談する」ということは、不得手なことであるはず。それは解っていても、いざ、自身がこのようなケースに出会った場合、お世辞にも専門職とは言えない自身の感情を無配慮にそのまま相手に発してしまうことがある。自戒を込めて記したいと思います。
見えない障害への想像力を高めること。クライエントを激励することは時に有効な場合があるかもしれないけれど、叱咤や叱責は如何なる場合でも不要なこと。立場や肩書に関係なく、どのような方であっても時に困りごとに直面する場合があること。そもそも私たち支援者は、人を叱責する存在ではなく、人に寄り添う存在であること。改めて、心に刻みたいと思います。

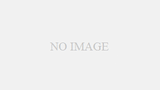
コメント