こんにちは。「社会福祉士相談所 LOVE」です。
2024年2月に、自宅の押し入れに乳児の遺体を放置したとして殺人と死体遺棄罪に問われた被告の裁判の一審判決が出ましたね…。
判決は懲役6年の実刑判決。補足すると検察の求刑は懲役7年、弁護側は懲役3年を求めていました。
当事業所代表は刑法等に精通している訳ではないので、この懲役6年という判決が妥当なのか、或いは重すぎるのか又は軽すぎるのかということは解かりませんし、何も言うことは出来ません。検察が求めた懲役7年や弁護側が求めた懲役3年ということについても同様です。
ただ、当事業所代表も自身が購読している新聞社のサイトで、この事件についての記事を改めて確認していくなかで社会福祉士として思うところはいくつかあります。今日はそれらについて記したいと思います。
まず、判決の中で裁判長が述べた、「衝動性はうかがわれず、ADHDの影響は大きいとはいえない」という部分については、私自身も発達障害のグレーゾーンと診断されている立場から、はっきりと「違うよね。」と考えます。
上手く言葉で表すことは難しいのですが…。発達障害(特性)のある方は、そうではない方と比較して、感じ方や考え方そのものが独特の場合が多い。逆に言えば、だからこそ診断が下りるのだと考えます。確かにその時の状況(環境)や精神状態によって、調子(特性)に波がある(いわゆるパニック状態かどうか)ことはあると思いますが、例えパニック状態ではなかったとしても、発達障害ではない方からすればおよそ考え付かない、判断(行動)の理由が解らない行動に及ぶことは充分にあり得ることだと考えます。
だから、発達障害がある方と接する際は、その方が発達障害を持っているということを常に踏まえておく必要があると考えます。それは、いわゆる「あの人は”障害者”なんだ…。」というレッテルを貼ることではなく、「時として、私たちとは違う感じ方や考え方をされる場合がある。」ということを理解しておくということだと考えます。
時期(記事)を遡ると、被告は妊娠の届出をしていなかったとあります。
保険料の滞納があったようなのでそれが発覚することを恐れたのかもしれません(保険料を納められていないので通院できなかったと、被告本人が語っています。)。また、被告が「行政に頼ると1人目のことが知られると思って、できなかった」と振り返っています(3人のこどものうち、1番目に生まれたこどもと、3番目に生まれたこどもは死産【死体遺棄】であり、2人目のこどもを殺害してしまった)。
願わくば保険料の支払いが難しくなった時点で、せめて1人目の妊娠に気付いた時点で、行政機関や支援機関、あるいは近隣や友人・知人等、何処かに繋がれていれば、相談出来ていればと思いますが、発達障害の方は、自分から助けを求めたり、自分から働きかけたり相談したりすることが苦手な場合が多いので、難しかったでしょうね…。また、保険料が「払えない」ことは想定外の事態(発達障害の方は、様々な場合を想像することが苦手なので、「問題なく払える」以外の可能性を想像して対応を考えておくことも難しいはず。)だったでしょうし、ましてや妊娠は非日常そのもの。「どうしよう、どうしよう…。どうしたら良いか解らない。」と独り苦悩されていた姿が、当事業所代表には容易に想像できます…。
そしてこれは障害のある方に限りませんが…。当事業所代表は、別件で「高松市こども計画(素案)」も拝読しましたが、高松市の子育て施策全般の認知度が低い状況ですし、「地域子育て支援拠点事業」に至っては、「今後も利用しない」という回答が53.7%にものぼっています(何故?)。様々な支援施策の周知啓発や、支援効果は勿論、接遇・対応面も含めて、「利用して良かった。また利用したい。」と思われる支援機関や支援者であることが求められますね。
最後に…。社会福祉支援は歴史的には生活困窮者への支援から始まっているけれど、戦後日本がどんどん豊かになり、「目に見えて生活に困窮している」という方が少なくなり、介護保険や障がい福祉サービス、孤独・孤立対策等新しい法制度が次々登場してくる中で、当事業所代表も含めて、生活困窮者への支援について、腰を据えて考えたり学んだり、対応したりといった経験が少なくなっている。改めて、生活困窮者への支援についても理解を深め、力量を高めていかなければならないと考えさせられました。
追記:2025.10.6 関連記事を執筆致しました。

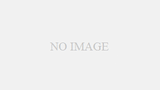
コメント