こんにちは。「社会福祉士相談所 LOVE」です。
先日、インターネットでこんな記事を目にしました。
介護職員への「カスハラ」が深刻 家族は「飲食店のようなサービスを求めてはいけない」理由
始めにはっきりと申し上げておきます。この記事自体を批判する意図は全くありませんが、この記事に書かれているようなことに家族やクライエントが注意をしなければならないとすれば、当事業所はとても違和感を覚えます。「当事業所の考え方」を改めて表明する機会にもなろうかと思えたので、この記事をベースに思うことを記します。
まず第一に、当事業所は、「カスタマーハラスメントの根底にあるのは、顧客意識。」(「私は客だ!」という意識)ではないかと考えますが、それのどこが悪いのでしょうか…。
確かに、自身や家族の過去の肩書等を根拠として、特別な優遇を求めるような言動(「自分は以前大企業の社長をやっていたのだから、他の利用者よりも優遇した対応をしろ。」等)や、職員の人格を貶めるような暴言や行為の要求(「馬鹿」等の発言や土下座や謝罪の強要)等は言語道断と思いますが、それ以外は(客観的には不適切な程の強い言葉であったとしても)、顧客としての要望を発しているだけではないかと思います。
そして、「クライエントとサービス提供事業者は対等な関係」私たちが大好きなとても美しい模範的な(?)言葉です。当事業所代表も20年程前社会福祉を学んだ際にそう教わりました。なので、少なくともここ20年以内に社会福祉を学んだ方や、現在社会福祉の現場で仕事をされている方にとっては(つまり『関係者』にとっては)常識であり、基本中の基本と思います。
片や、当事業所代表の親は70代であり、社会福祉を学んだことも社会福祉の仕事に就いたこともなく、いわゆる接客業に永く携わってきた人です。その親が常に言っていたことは、「顧客とサービス提供事業者が対等な関係なんてあり得ない。お金を払う顧客の方が上に決まっている。」という言葉。なんなら、「客と言うのは、購入して頂いて初めて客になる。何も購入せず帰ったのなら、客ではない。」、更には「1万円の商品を購入してくれた人と、1,000円の商品しか購入してくれなかった人の対応に差を付けるのは当然。」というようなことも言っていました。
それぞれの主張の善し悪しを審判したい訳ではなく、「私たち関係者が常識と考えていることが、そうではない方々もいらっしゃるのではないか。むしろ、私たちの”顧客”は、そういった方々の方が圧倒的に多いのではないか。」ということを言いたいのです。
そして、記事にある「現場が忙しい食事介助の時間などは避けるべき」とか、「通常の営業時間内に連絡を」。これも、違和感を覚えます。
当事業所代表も以前、成年後見人としてデイサービスを利用されている方の支援をしたことがありますが、デイサービスに連絡する際にはあえて夕方(16時代)の時間帯は避け、17:30以降に連絡をしておりました。
また現在、当事業所代表個人として関わっているこども食堂関連の活動のことで、事務局を担っている地域子育て支援拠点事業を運営している団体様に連絡をすることもありますが、当事業所代表はいわゆるお昼の時間帯が時間を取りやすいので連絡を入れることが多いのですが、そんな時は「電話の方が早いかな。」と思うことでもあえてメールで連絡しています。
それは、私自身が以前、デイサービスが併設されている特別養護老人ホームでの勤務経験があり、夕方の時間帯は送迎で大変な時間帯だということを知っているからです。また、学生時代に地域子育て支援拠点事業でボランティアをさせて頂いた経験があるので、「お昼時は職員の方々も利用されている親子と一緒にお昼ご飯を食べる、関係構築のためのとっても大切な時間。」であることを知っているからです。
つまり、たまたま経験があり、現場の状況が想像出来るので、少しだけ配慮しているということ。経験がない(可能性が高い)ご家族に、それを求めますか?もし、それをお願いしたいのであれば、丁寧に「食事時は利用者様の食事介助を職員総出で行わなければならず、一瞬眼を離した隙に喉に詰めてしまわれて命が危険にさらされることもあるので、もしも可能であればその時間帯は避けて頂けないでしょうか。」と丁寧に説明し、お願いする必要があるのではないでしょうか。「そんなこと解るでしょ!」と言うのは、申し訳ないけれど職員側の驕りと感じます。
また、入所施設は24時間365日対応のハズ。「通常の営業時間」って何時~何時でしょうか…。
これは、「昼間の時間帯限定で事務所で勤務している、事務員や生活相談員、施設長等の管理職の勤務時間帯」を指していると考えられます。施設に、「事務所は何時~何時まで対応されていますか?」と尋ねれば教えて頂けると思います。でも、これも例えば「平日の9時~17時半」というようなところが多いのです…。いわゆる民間(営利)企業でお仕事されているご家族様は、場合によっては19時とか20時以降までお仕事されている方もいらっしゃるはずですし、土日しかお休みが取れない方もいらっしゃるはず…。「お互いの歩みよりが大切」と言いながら、事業所側はそういった方々に「歩み寄って」いるのでしょうか。一方的に通達してはいないでしょうか…。
余談ですが、当事業所が営業時間を定めていないのはそういった理由からです。本当はかっこよく、「365日24時間営業」と言いたいところですが、現状代表兼職員の個人(自分だけでの)対応のため、それを言うと詐欺になってしまう…。夜間は事前に相談予約が入っていない限り、睡眠を取っていますし、相談予約等が入っていない時に買い物や自身の受診等で外出している場合もあるので、頂いた連絡に直ぐに応答出来ない時もあり得ますし、例えば深夜帯の相談予約であれば、「もしも可能であれば、昼間の時間に対応させて頂くことは出来ないでしょうか…。」とお願いすることもあるかもしれません。
当事業所が日中の常識的な時間を「営業時間」として定めれば、簡単に解決出来ることですし、もしかしたらその方がお客様にも分かりやすいかもしれません。でも…。深夜帯等、いわゆる『常識』からは少し外れた時間帯に連絡してこられる方がいた場合、相談を受ける受けない以前に、まず、「その理由を知りたい」と当事業所は思います。多くの日本人であれば、深夜帯は休んでいたいはず…。にも関わらずの理由を知りたい。もしかしたら、精神的な不調で夜しっかりと眠ることが出来ず、不安で苦しい時間を過ごされているのかもしれないし、お仕事等の活動がとっても忙しく、そんな時間にしか連絡出来ないのかもしれないし、家族等が寝静まった後でないと連絡できない等の事情があるのかもしれない…。当事業所の約束①「お話を聴かずにお断りすることは致しません」です。
記事中にある「介護サービスはあくまでも公的制度の中で提供される」ものということについても、私たち従事者からすれば当たり前の常識でも、そうではない方にとってはなかなかに難しい表現でしょうし、そもそも現実に生存して活動している人間は、「書類上に書かれていないこと」が起こることは当たり前にあるはず…。それを全て対応せよとは言わないけれど、「もう一度一緒に契約書を確認しながら、平易な言葉で丁寧に説明する。」ことはあってもよいのではないかと考えます。
最後に…。当事業所代表の恥をさらすことになってしまいますが、当事業所代表もこの記事で言うところのカスタマーハラスメントを行ってしまった経験がございます。8年程前、将来(親亡き後)への不安や、仕事で上手くいかないこと、二次障害への不安等々、いろいろなことで不安感が急激に高まり、「自分を支援してくれる人」を求めて、社会福祉士の方と任意後見契約を締結して、支援を受ける側(顧客)になった経験がありましたが、ごく短期間で契約解消されてしまった経験があります…。
こういった場合の定期面接って、多くの場合「月1回」という場合が不文律のように決まっている…。でも、極度に不安感が強かった当時の私にとって、その頻度は長過ぎた…。当時の私には出来れば週に数回、どんなに長くても2週に1回くらいの面接頻度が『安心のために』必要だった…。私も言葉でそう説明出来れば良かったのだけれど、当時自分の心理状態を冷静に見つめることが出来ず、「私は…。」のIメッセージで自分の不安や辛さを伝えれば良かったのに、無意識のうちに、「あなたは解ってくれない。」と、強い態度で相手を責めた(最初に書いた顧客意識だと思う)。相手も、「この人(私)も社会福祉士」という認識があったから、「信頼関係が築けない」となり、契約解消となった。
当事業所の約束③「福祉専門職の方であっても、一相談者として対応致します。」というのは、代表自身の苦く、苦しい経験から導き出した、当事業所の支援哲学です。

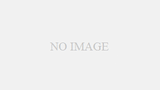
コメント